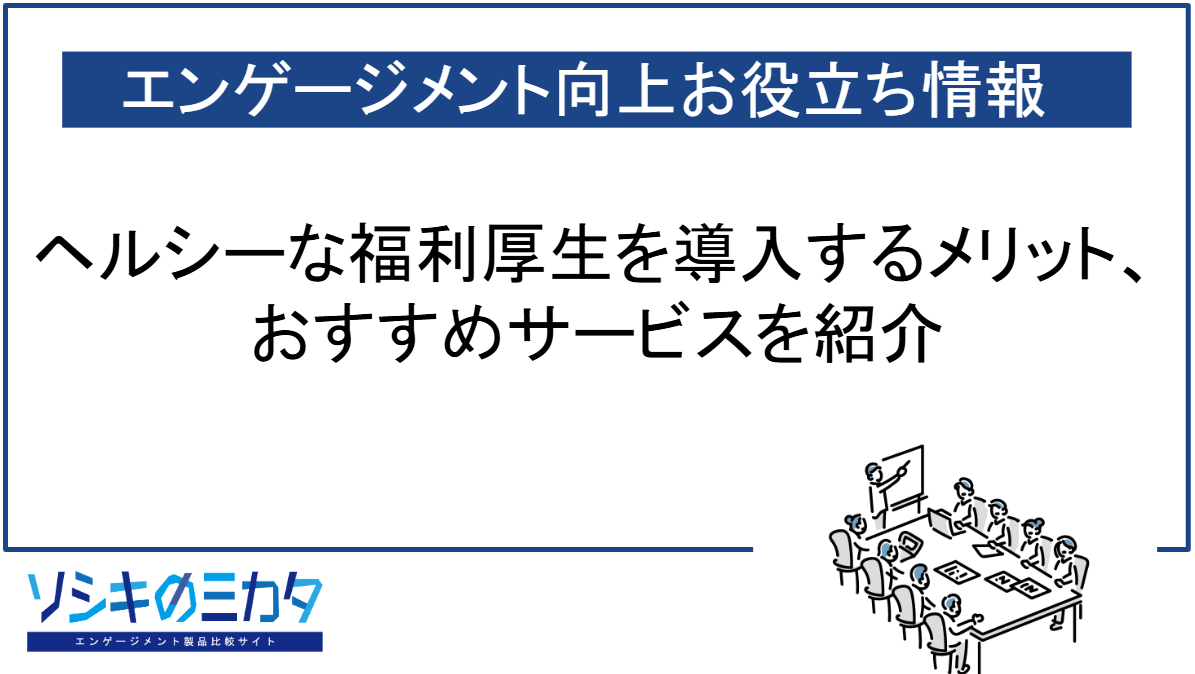ヘルシーな福利厚生を導入するメリット、おすすめサービスを紹介
人材定着に課題を抱える企業が増え続けることを背景に、従業員の健康面を意識して、ヘルシーな福利厚生を導入する企業が増えています。
今回は、フィジカルヘルス・メンタルヘルスの両面で従業員に優しい、ヘルシーな福利厚生について紹介します。
ヘルシーな福利厚生とは?
ヘルシー福利厚生とは、従業員の身体的・精神的健康をサポートすることを目的とした福利厚生制度の総称です。
従来の福利厚生が給与補填や生活支援に重点を置いていたのに対し、ヘルシー福利厚生は「健康」を軸に、従業員のウェルビーイング(心身の幸福)向上を目指します。
具体的には、以下のような取り組みが含まれます。
- 食事面のサポート:社食サービス、置き型健康食、栄養バランスを考慮した食事補助
- 運動促進:フィットネスジムの法人契約、スポーツイベント、健康アプリの提供
- メンタルヘルスケア:カウンセリングサービス、ストレスチェック、マインドフルネスプログラム
- 健康診断の充実:人間ドックの補助、オプション検査の提供
- 休養・リフレッシュ:マッサージサービス、睡眠改善プログラム
福利厚生の「厚生」が持つ本来の意味
「厚生」という言葉には、「生活を健康で豊かなものにする」という意味が込められており、福利厚生という制度そのものが、本来は従業員の健康を守り、充実した生活を実現することを目指しています。
ヘルシー福利厚生は、この福利厚生の原点に立ち返り、従業員の健康を最優先に考える取り組みといえます。
健康経営との関係性
ヘルシー福利厚生は「健康経営」を実現するための重要な手段の一つです。
健康経営とは、1980年代にアメリカで提唱された「ヘルシーカンパニー思想」を基に発展した概念で、「健康な従業員こそが、収益性の高い企業をつくる」という考え方です。
日本では経済産業省が「健康経営銘柄」や「健康経営優良法人」の認定制度を設け、積極的に推進しています。
健康経営とヘルシー福利厚生の違い
| 項目 | 健康経営 | ヘルシー福利厚生 |
|---|---|---|
| 概念 | 経営戦略・経営手法 | 具体的な施策・サービス |
| 目的 | 企業の生産性向上と持続的成長 | 従業員の健康維持・増進 |
| アプローチ | トップダウン型の経営課題 | 従業員に直接提供する支援 |
| 評価指標 | 企業価値、業績、認定取得 | 従業員満足度、利用率 |
健康経営という「戦略」を実現するために、ヘルシー福利厚生という「具体的な施策」を導入する、という関係性にあります。
ヘルシーな福利厚生が注目される背景
労働人口の減少と人材確保の課題
日本は深刻な少子高齢化により、労働人口が年々減少しています。企業にとって優秀な人材の確保と定着は、経営の最重要課題となっています。
厚生労働省の調査によると、就職活動中の求職者が企業選びの際に重視する項目の上位に「福利厚生の充実度」が挙がっており、特に健康面をサポートする福利厚生は高い人気を集めています。
働き方改革と従業員のウェルビーイング重視
働き方改革の推進により、企業は従業員の労働環境改善に取り組むようになりました。
単に労働時間を削減するだけでなく、従業員が心身ともに健康で、充実した働き方ができる環境を整えることが求められています。
コロナ禍による健康意識の高まり
新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの人々が健康の重要性を再認識しました。
テレワークの普及によって運動不足や食生活の乱れが問題となり、企業による健康サポートの必要性が増しています。
また、メンタルヘルスの問題も深刻化しており、心のケアを含めた包括的な健康支援が求められるようになっています。
医療費・社会保険料の負担増加
高齢化社会の進展により、企業が負担する社会保険料は年々増加しています。
日本経済団体連合会の調査では、法定福利費が現金給与総額に占める割合は増加傾向にあり、企業の経営を圧迫する要因となっています。
従業員の健康を維持することで、医療費の削減や欠勤率の低下につながり、結果的にコスト削減効果が期待できます。
これが、予防医学の観点からヘルシー福利厚生が注目される理由の一つです。
法定外福利厚生のトレンド変化
従来の法定外福利厚生は、レクリエーションや慰安旅行などが中心でしたが、近年は大きく様変わりしています。
福利厚生のトレンド変化
- 従来型:社員旅行、忘年会、保養所の提供
- 現代型:健康管理支援、自己啓発・スキルアップ支援、育児・介護支援、ヘルスケアサポート
リクルートキャリアの調査による福利厚生のトレンドトップ3には、健康関連の福利厚生が複数ランクインしており、企業の関心の高さがうかがえます。
ヘルシーな福利厚生の種類と分類
ヘルシーな福利厚生は、大きく4つのカテゴリーに分類できます。
1.食事・栄養サポート型
従業員の食生活を改善し、栄養バランスの取れた食事を提供する福利厚生です。
主なサービス形態
- 社員食堂:企業が運営する食堂で、栄養バランスを考慮した食事を提供
- 置き型社食サービス:オフィスに冷蔵庫や什器を設置し、健康的な食品を提供
- 食事補助(ICカード型):提携店舗で使えるICカードを従業員に配布
- 弁当配達サービス:栄養管理された弁当を定期配送
- 軽食・おやつサービス:健康的なスナックやドリンクの提供
メリット
- 従業員の食生活改善による健康増進
- 昼食の外出時間削減による業務効率化
- 食事を通じたコミュニケーション活性化
- 24時間利用可能なサービスなら、夜勤や変則勤務にも対応
2. 運動・フィットネス型
身体活動を促進し、運動習慣の定着を支援する福利厚生です。
具体例
- フィットネスジムの法人契約・利用補助
- 社内フィットネスルームの設置
- ヨガ・ストレッチ教室の開催
- ウォーキングイベント・スポーツ大会
- 健康管理アプリの提供(歩数計測、運動記録)
期待できる効果
- 生活習慣病の予防
- 肩こり・腰痛などの身体的不調の軽減
- ストレス解消
- チームビルディング
3. メンタルヘルスケア型
心の健康を守り、ストレス管理を支援する福利厚生です。
厚生労働省の「労働安全衛生調査」によると、「現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスを感じる事柄がある」と回答した労働者は約58%に上ります。
主な取り組み
- 産業カウンセラー・臨床心理士による相談窓口
- ストレスチェック制度の充実
- マインドフルネス・瞑想プログラム
- マッサージ・リラクゼーションサービス
- メンタルヘルス研修
重要性
- メンタル不調による休職・離職の予防
- 従業員のパフォーマンス維持
- 職場の心理的安全性の向上
4. 総合的健康管理型
予防医学の観点から、包括的に従業員の健康をサポートする福利厚生です。
サービス内容
- 定期健康診断の充実(人間ドック、脳ドック)
- 保健師・産業医による健康相談
- 健康セミナー・健康教育プログラム
- 睡眠改善プログラム
- 禁煙サポート
- 女性の健康支援(婦人科検診、妊活支援)
導入のポイント
- データに基づく健康課題の把握
- 継続的なフォローアップ体制
- プライバシーへの配慮
ヘルシーな福利厚生の導入メリット
企業側のメリット
従業員満足度の向上と離職率の低下
ヘルシー福利厚生の充実は、従業員満足度を大きく向上させます。
「会社が自分の健康を気にかけてくれている」という実感は、企業への信頼感とエンゲージメントを高めます。
特に若手世代は、給与水準だけでなく、ワークライフバランスや福利厚生を重視する傾向が強く、健康支援の手厚い企業は人材定着率が高いというデータがあります。
採用力の強化
優秀な人材の確保は、企業の競争力を左右します。
求人票や採用サイトでヘルシー福利厚生をアピールすることで、求職者に「従業員を大切にする企業」という印象を与えられます。
健康経営優良法人の認定を受けた企業は、求人への応募数が平均で約1.5倍増加するというデータもあります。
生産性の向上
健康な従業員は、集中力が高く、ミスが少なく、クリエイティビティも向上します。
また、体調不良による欠勤(アブセンティーズム)や、出勤はしているものの体調不良で生産性が低下する状態(プレゼンティーズム)を削減でき、企業全体のパフォーマンス向上につながります。
医療費・社会保険料の抑制
予防医学の観点から従業員の健康を維持することで、将来的な医療費の削減が期待できます。
また、健康保険組合の医療費負担が軽減されることで、保険料率の上昇を抑制できる可能性があります。
企業イメージの向上
健康経営に積極的に取り組む企業は、社会的評価が高まります。
ESG投資の観点からも、従業員の健康に配慮する企業は投資家から好意的に評価されます。
また、「健康経営銘柄」「健康経営優良法人」「ホワイト500」などの認定を取得することで、対外的な信頼性が向上します。
従業員側のメリット
健康維持・増進
食事、運動、メンタルヘルスなど、多角的なサポートを受けることで、健康的な生活習慣を身につけやすくなります。
特に独身世帯や単身赴任者は食生活が乱れがちですが、社食サービスや栄養バランスの取れた食事補助があることで、健康リスクを軽減できます。
経済的負担の軽減
健康診断の補助、フィットネスジムの利用料補助、食事補助など、個人で負担すれば高額になるサービスを、企業の支援によって低コストまたは無料で利用できます。
ワークライフバランスの改善
職場で手軽に食事が取れることで昼休憩の時間を有効活用できたり、社内でリラクゼーションサービスを受けられたりすることで、プライベート時間を充実させることができます。
コミュニケーションの活性化
食事スペースやフィットネス施設を通じて、部署を超えた交流が生まれやすくなります。
カジュアルなコミュニケーションは、業務上の協力関係を円滑にし、イノベーションを促進します。
おすすめのヘルシーな福利厚生サービス12選
snaq.me office(スナックミーオフィス)
サービス概要
snaq.me officeは、無添加・低糖質・ナチュラル素材にこだわった置き菓子・ドリンク・軽食を提供する法人向けオフィスコンビニサービスです。
特徴
- 無添加へのこだわり:白砂糖、人工添加物、マーガリン、ショートニング不使用
- 豊富なバリエーション:100種類以上のおやつから毎月新作を含むセットが届く
- 費用負担ゼロプランあり:企業負担ゼロ円のプランも選択可能
- 全国対応:日本全国どこでも配送可能
- 初期費用無料:月額利用料・初期費用・更新費・送料・備品代すべて無料
こんな企業におすすめ
- 健康経営優良法人の認定を目指している企業
- 従業員の健康意識を高めたい企業
- コンビニが近くにないオフィス
- 出社率を向上させたい企業
オフィスおかん
サービス概要
管理栄養士監修の健康的なお惣菜を、オフィスの冷蔵庫に定期配送する置き型社食サービスです。
特徴
- 1品100円:手頃な価格で栄養バランスの取れた食事
- 24時間利用可能:夜勤や早朝勤務にも対応
- 全国3,000拠点以上の導入実績
- 従業員満足度94%
- 30日以上の賞味期限:輪番出社やテレワークにも対応
こんな企業におすすめ
- 社員食堂の運営が難しい中小企業
- 24時間稼働する工場や医療機関
- 栄養バランスを重視したい企業
OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)
サービス概要
新鮮な野菜やフルーツを中心とした「オフィスでやさい」と、お惣菜中心の「オフィスでごはん」の2プランを展開。
特徴
- 新鮮なサラダ・フルーツ:週2回の定期配送
- 2,000拠点の導入実績
- サービス継続率98.4%
- 健康志向の高いメニュー
こんな企業におすすめ
- 野菜不足が課題となっている企業
- ヘルシー志向の従業員が多い企業
チケットレストラン
サービス概要
ICカード配布型の食事補助サービス。全国25万店舗以上の加盟店で利用可能。
特徴
- 利用率98%、継続率99%、満足度93%
- テレワークにも対応:自宅近くの店舗でも利用可
- 多様な食事スタイルに対応
こんな企業におすすめ
- ハイブリッドワークを導入している企業
- 社員食堂の設置が難しい企業
オフィスdeリラックス
サービス概要
プロの施術師がオフィスに出張訪問し、マッサージやリラクゼーションを提供。
特徴
- 利用率90%以上
- メンタル・フィジカル両面のケア
- 都市部中心のサービス(東京・大阪・名古屋・札幌)
こんな企業におすすめ
- デスクワーク中心の企業
- 肩こり・腰痛の訴えが多い職場
人間ドック・健康診断の充実プログラム
定期健康診断に加え、人間ドック、脳ドック、がん検診などの費用を補助するプログラム。
メリット
- 早期発見・早期治療による重症化予防
- 健康意識の向上
フィットネスジム法人契約
大手フィットネスチェーンとの法人契約により、従業員が割引料金で利用できるサービス。
代表的なサービス
- ルネサンス法人会員
- コナミスポーツクラブ法人契約
- セントラルスポーツ法人プラン
産業カウンセラー・EAPサービス
メンタルヘルスの専門家による相談窓口を提供。
特徴
- 電話・オンラインで匿名相談可能
- 24時間365日対応のサービスもあり
- プライバシー厳守
健康管理アプリ
歩数や体重、食事内容などを記録し、健康状態を可視化するアプリ。
代表的なアプリ
- Wellness to Go
- ヘルスケア(Apple)
- Google Fit
睡眠改善プログラム
質の高い睡眠をサポートするプログラム。
内容例
- 睡眠に関するセミナー
- 睡眠計測デバイスの貸与
- 睡眠コンサルティング
禁煙サポートプログラム
禁煙を希望する従業員を医学的にサポート。
サポート内容
- 禁煙外来の費用補助
- ニコチンパッチの提供
- 禁煙相談窓口
女性の健康支援プログラム
女性特有の健康課題をサポート。
内容例
- 婦人科検診の費用補助
- 妊活支援セミナー
- 更年期サポート
ヘルシーな福利厚生の導入の流れと成功のポイント
ヘルシー福利厚生導入の5ステップ
ステップ1:現状分析と課題抽出
まず、自社の現状を把握することから始めます。
分析すべきポイント
- 従業員の健康状態(健康診断データ、ストレスチェック結果)
- 離職率・欠勤率
- 従業員へのアンケート結果
- 既存福利厚生の利用状況
ステップ2:目的とKPIの設定
ヘルシー福利厚生の導入目的を明確にし、測定可能な指標(KPI)を設定します。
KPI例
- 従業員満足度スコア
- 利用率
- 健康診断の有所見率
- 離職率の変化
- アブセンティーズムの削減
ステップ3:予算設定とサービス選定
予算を決定し、複数のサービスを比較検討します。
比較ポイント
- 初期費用・月額費用
- 従業員負担額
- サービス内容の充実度
- 導入実績
- サポート体制
ステップ4:導入準備と周知
サービス導入が決まったら、社内への周知を徹底します。
周知方法
- 社内説明会の開催
- イントラネット・社内報での告知
- ポスター・チラシの掲示
- デモンストレーション
ステップ5:運用開始と効果測定
サービスを開始したら、定期的に効果測定を行い、必要に応じて改善します。
ヘルシーな福利厚生導入における成功のポイント
ポイント1:従業員のニーズを正確に把握する
アンケートやヒアリングを通じて、従業員が本当に求めているサービスを導入することが重要です。
ポイント2:経営層のコミットメント
健康経営は経営戦略です。経営トップが率先して推進することで、組織全体に浸透します。
ポイント3:継続的な情報発信
導入しただけで満足せず、定期的に利用を促す情報発信を続けることが、利用率向上の鍵です。
ポイント4:複数の施策を組み合わせる
食事、運動、メンタルケアなど、多角的なアプローチを組み合わせることで、より高い効果が期待できます。
ポイント5:小規模から始める
いきなり大規模な導入をするのではなく、パイロット的に小規模で始め、効果を検証しながら拡大していく方が成功確率が高まります。
ヘルシーな福利厚生導入の際によくある質問(FAQ)
Q1. ヘルシーな福利厚生の導入にはどのくらいの費用がかかりますか?
A. サービスの種類や従業員数によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 置き型社食サービス:従業員一人当たり月額1,000~3,000円
- ICカード型食事補助:従業員一人当たり月額2,000~5,000円
- フィットネス補助:従業員一人当たり月額500~2,000円
- 産業カウンセラー:月額10万円~30万円(企業規模による)
初期費用無料のサービスも多く、小規模から始めることができます。
Q2. 中小企業でも導入できますか?
A. もちろん可能です。
むしろ中小企業こそ、限られた予算で効果的に従業員満足度を高められるヘルシー福利厚生はおすすめです。
置き型社食サービスやICカード型食事補助は、初期費用ゼロで始められるものも多く、従業員数が少なくても導入しやすい設計になっています。
Q3. テレワーク中心の企業でも効果はありますか?
A. テレワーク環境でも活用できるヘルシー福利厚生があります。
- ICカード型食事補助:自宅近くの提携店舗で利用可能
- オンラインカウンセリング:自宅から相談できる
- 健康管理アプリ:場所を問わず利用できる
- オンラインフィットネス:自宅でヨガやトレーニングができる
出社日が少ない場合は、場所を選ばないサービスを選ぶことがポイントです。
Q4. 従業員負担が必要なサービスと、無料で提供するサービス、どちらが良いですか?
A. 一概には言えませんが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
従業員負担ありのメリット
- 利用者の自己負担があることで、真に必要とする人が利用する
- 企業の負担が軽減される
完全無料のメリット
- 利用のハードルが下がり、利用率が向上
- 「会社からのプレゼント」として従業員満足度が高まる
多くの企業では、企業と従業員が費用を分担する形(例:企業70%、従業員30%)を採用しています。
Q5. 利用率が低い場合、どう改善すれば良いですか?
A. 利用率が低い原因を特定し、対策を講じましょう。
よくある原因と対策
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| サービスの存在を知らない | 定期的な周知活動、社内報での紹介 |
| 利用方法がわからない | 説明会の開催、マニュアルの整備 |
| 利用しにくい時間帯・場所 | 設置場所や提供時間の見直し |
| メニューや内容が魅力的でない | 従業員アンケートでニーズを把握 |
| そもそもニーズがない | サービス内容の再検討 |
特に導入初期は、経営層や管理職が率先して利用することで、従業員の心理的ハードルが下がります。
Q6. 健康経営優良法人の認定を取得するには、どのような取り組みが必要ですか?
A. 健康経営優良法人の認定には、以下のような項目が評価されます。
大項目(一例)
- 経営理念・方針
- 組織体制
- 制度・施策実行
- 評価・改善
- 法令遵守・リスクマネジメント
具体的には、健康宣言の策定、健康づくり担当者の設置、定期健康診断の実施率、ストレスチェックの実施、健康増進施策の展開などが求められます。
ヘルシー福利厚生の導入は、「制度・施策実行」の項目で大きく評価されます。
詳細は経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」のWebサイトをご確認ください。
Q7. 導入後、どのくらいの期間で効果が表れますか?
A. 効果が表れる時期は、指標によって異なります。
短期(1~3ヶ月)
- 従業員満足度の向上
- 利用率の上昇
- 社内コミュニケーションの活性化
中期(6ヶ月~1年)
- 離職率の低下
- 採用応募数の増加
- 欠勤率の改善
長期(1年~3年)
- 健康診断の有所見率改善
- 医療費の削減
- 生産性の向上
健康改善は時間がかかるため、長期的な視点で取り組むことが重要です。
Q8. 派遣社員やアルバイトにも提供すべきですか?
A. 雇用形態に関わらず、すべての従業員に提供することをおすすめします。
理由
- 公平性の観点:雇用形態による差別を避ける
- 離職率の改善:非正規社員の定着率向上
- 職場の一体感:全員が同じ福利厚生を享受することでチームワーク向上
ただし、予算の制約がある場合は、段階的に対象を拡大する方法もあります。
Q9. 健康経営と働き方改革の違いは何ですか?
A. 両者は密接に関連していますが、焦点が異なります。
働き方改革
- 焦点:労働時間、働き方の柔軟性
- 目的:長時間労働の是正、ワークライフバランスの実現
- 具体策:残業削減、有給取得促進、テレワーク導入
健康経営
- 焦点:従業員の心身の健康
- 目的:健康維持・増進による生産性向上
- 具体策:健康診断、運動促進、食事支援、メンタルケア
働き方改革で労働環境を整え、健康経営で心身のサポートをする、という相互補完的な関係にあります。
Q10. 導入時に従業員から反対意見が出た場合、どう対応すれば良いですか?
A. 反対意見が出る理由を丁寧にヒアリングし、不安を解消することが大切です。
よくある反対意見と対応
「個人の食事に会社が介入しないでほしい」 → 強制ではなく、あくまで選択肢の一つとして提供することを説明
「プライバシーが心配」 → 健康データの取り扱いについて、厳格なルールを説明
「利用しない人にとって不公平」 → 多様な福利厚生を用意し、誰でも何かしら利用できる状態を目指す
導入前の説明会で、目的やメリットを丁寧に伝えることで、理解が深まります。
従業員に喜ばれるヘルシーな福利厚生を導入しませんか?
今回は、従業員に人気の健康に配慮したヘルシーな福利厚生の導入メリットやおすすめのサービスなどを紹介しました。
従業員に長く活躍してもらうためには、健康づくりのサポートを行える福利厚生を導入することがおすすめです。
「福利厚生を充実させたいけれど、予算もスペースも限られている」
「何から始めればいいかわからない」
そんな人事担当者の方は、まずは少人数から始められる置き菓子サービスや、トライアル期間のあるサービスから検討してみてはいかがでしょうか。
ソシキのミカタがおすすめする福利厚生の「snaq.me office (スナックミーオフィス)」の詳細は下記ボタンのリンクからご確認ください。