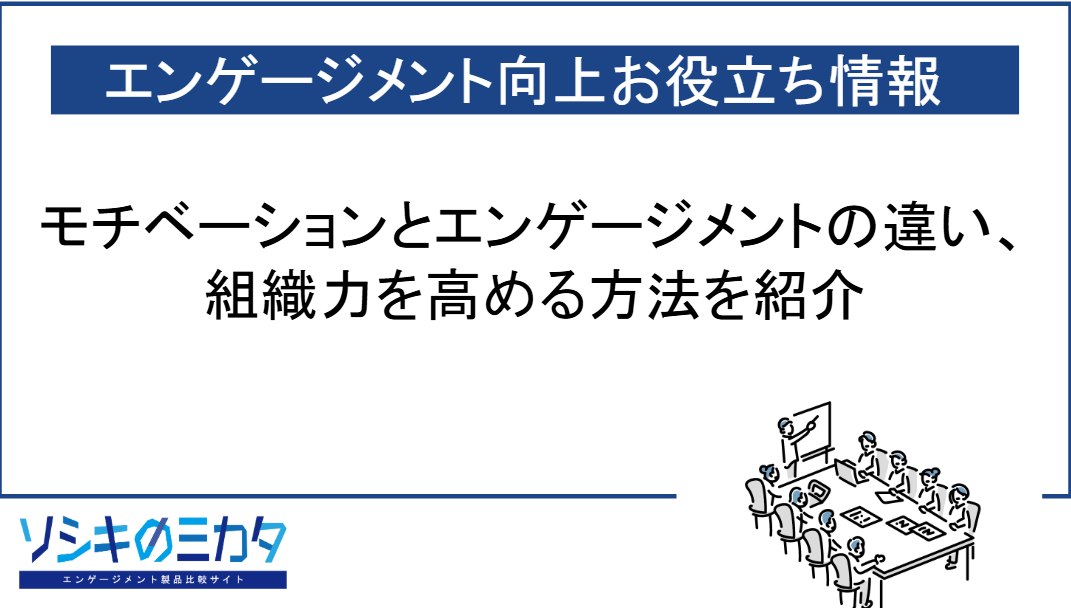モチベーションとエンゲージメントの違い、組織力を高める方法を紹介
近年、人材戦略において重要視されている従業員のモチベーションとエンゲージメント。
どちらも組織の活性化に不可欠な要素ですが、その違いを明確に理解できているでしょうか。
モチベーションは、目標達成に向けた意欲を指し、個人の内発的な動機に大きく左右されます。
一方、エンゲージメントは、組織への愛着や貢献意欲を表し、従業員と組織の関係性によって醸成されるものです。
本記事では、このモチベーションとエンゲージメントの2つの概念の違いを解説し、それぞれの向上に向けた具体的な施策を紹介します。
従業員の「モチベーション」と「エンゲージメント」が重要である理由
現代のビジネス環境は、少子高齢化による生産年齢人口の減少という構造的な課題に直面しています。
総務省のデータによると、生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少が続いており、2050年には2021年から29.2%減少して5,275万人になると推計されています。
このような状況は、企業にとって構造的な人手不足を招き、優秀な人材の獲得競争を激化させています。
また、労働市場全体の流動化も加速しており、特に若年層や中堅層を中心に転職が活発化しています。
2023年の転職率は7.5%に達し、これは2016年以降で最も高い水準となりました。
若年・中堅層(15~34歳)の転職率の増加割合は、総数の増加割合の約3倍にも上るとのデータもあります。
この高い流動性は、単に人材を「獲得」するだけでなく、自社で活躍する従業員を「定着」させることの重要性を高めています。
さらに、近年ではリモートワークをはじめとする働き方の多様化が急速に進展しました。
柔軟な働き方が可能になった一方で、オフィスでの偶発的なコミュニケーションが減少し、従業員間のつながりや組織への帰属意識、一体感が希薄になりやすいという課題も顕在化しています。
企業には、物理的な距離があっても従業員が組織とのポジティブな関係性を築けるよう、新たなアプローチで組織と個人の「つながり」を再構築することが求められているのです。
加えて、現代は「VUCA時代」と呼ばれ、将来の予測が困難で変化が激しい状況が続いています。
このような不確実性の高い環境で企業が持続的に成長していくためには、経営層や管理職の指示を待つだけでなく、従業員一人ひとりが変化を敏感に察知し、自律的に考え、行動する力が不可欠です。
従業員の内発的な意欲や、組織の目標達成に向けた積極的な関与、つまり高いモチベーションとエンゲージメントが、新しいアイデアや価値創造につながり、企業の競争力強化に直結します。
これらの理由から、従業員のモチベーションとエンゲージメントへの取り組みは、今や企業経営における最重要課題の一つとなっています。
モチベーションとエンゲージメントの定義
「エンゲージメント」、そして「モチベーション」という言葉が、それぞれどのような意味合いを持つのか、その基本的な定義をそれぞれ紹介します。
エンゲージメントとは|組織と従業員のポジティブな心理的つながり
エンゲージメントとは、従業員が自身の所属する組織に対し、能動的かつポジティブに抱く心理的な結びつきを指します。
具体的には、組織の目標や価値観への共感に基づき、「この組織の一員として貢献したい」、「組織と共に成長したい」といった愛着や貢献意欲、さらには主体的に組織に関わろうとする意志などが含まれます。
これは、単に仕事内容や待遇に満足している状態とは異なり、組織の成功のために自ら進んで行動を起こそうとする状態を指すと言えます。
このエンゲージメントは、ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)で示される3つの側面から構成されるのが代表的です。
これらは以下の通りです。
- 活力(Vigor):仕事からエネルギーを得て、困難にも立ち向かえる状態。
- 熱意(Dedication):仕事に意義を見出し、誇りやインスピレーションを感じる状態。
- 没頭(Absorption):仕事に深く集中し、時間を忘れるほど打ち込んでいる状態。
エンゲージメントが高い従業員は、組織のビジョンに深く共感し、その実現に向けて積極的に行動します。
また、組織が抱える課題を他人事ではなく自分ごととして捉え、自発的に改善策を提案するなど、組織全体のパフォーマンス向上に貢献しようと努める傾向があります。
モチベーションとは|個人の目標達成に向けた意欲・動機づけ
モチベーションとは、個人の目標を達成しようとする際に生まれる意欲ややる気を指します。
これは、特定の行動を引き起こし、それを維持するための心理的なエネルギーや原動力である動機づけと言えるでしょう。
モチベーションには大きく分けて二つの種類があります。
一つは内発的動機づけです。
これは、仕事そのものに対する興味・関心や、そこから得られる達成感、自己成長への欲求など、個人の内面から湧き出る要因によるものです。
「仕事が楽しいから」「自分のスキルを高めたいから」といった理由で行動する場合がこれにあたります。
もう一つは外発的動機づけです。
こちらは、報酬、昇進、他者からの評価、あるいは罰則の回避など、外部からの刺激や働きかけによって生まれる動機です。
「目標を達成したらボーナスをもらえるから」「評価を上げるために頑張ろう」といった外部要因が行動のきっかけとなる場合が該当します。
モチベーションは、あくまで個人の目標達成に向けられたエネルギーであり、必ずしもその方向性が組織全体の目標と一致するとは限らない点も重要なポイントです。
【一覧比較】モチベーションとエンゲージメントの明確な違い
モチベーションとエンゲージメントの具体的な違いについて紹介します。
違い①:関係性の方向性(双方向か、一方向か)
エンゲージメントは、組織と従業員間の「双方向」的な関係性を指します。
企業が従業員の働きがいやキャリア形成を支援する一方で、従業員もまた組織の成功に貢献したいという意欲を持ち、相互に影響を与え合う信頼関係に基づいています。
これは単に与えられる満足度とは異なり、組織と個人が共に成長していくようなポジティブな結びつきと言えるでしょう。
対照的に、モチベーションは、主に個人の中から特定の目標達成に向けて生まれる「一方向」のエネルギーや動機づけです。
個人の内的な欲求や外的な要因によって引き起こされる意欲が源泉であり、そのベクトルは個人の目標達成に強く向かいますが、必ずしも組織全体の目標や貢献と直接的に一致するわけではありません。
このように、エンゲージメントは組織と従業員の相互作用による関係性の強さを示すのに対し、モチベーションは個人の行動の原動力そのものを表す概念である点が、方向性における大きな違いです。
違い②:持続性の長さ(長期的か、短期的か)
モチベーションは、特定の目標達成や昇給、インセンティブといった外部からの報酬や評価(外発的動機づけ)に強く依存する傾向があります。
これらの外部刺激がなくなると、その意欲ややる気は比較的早く低下しやすい性質を持ちます。
例えば、特定のプロジェクトが完了したり、ボーナス支給が終わったりすると、一時的に高まっていたモチベーションが維持できなくなることがあります。
このように、モチベーションは外部要因に左右されやすく、短期的な変動を伴う概念と言えます。
一方、エンゲージメントは、組織のビジョンや事業内容への深い共感、自身の仕事に対するやりがいや成長実感(内発的動機づけ)など、従業員の内面から湧き出る要因に根差しています。
組織との間に築かれた信頼関係や愛着が土台となるため、一度醸成されると簡単には揺らぎにくく、長期的に持続する性質があります。
モチベーションが特定の出来事によって燃え上がる「点」や、目的達成まで続く「線」のような一時的なものであるのに対し、エンゲージメントは組織との安定した「状態」を示すのです。
持続的な組織の成長を実現するためには、この安定したエンゲージメントの向上が不可欠と言えるでしょう。
違い③:影響の範囲(組織全体か、個人か)
モチベーションは、個人の目標達成に向けた意欲や動機づけであり、その影響範囲は主に個人のパフォーマンス向上に限定されます。
例えば、特定のインセンティブによって個人の営業成績が上がるといった効果が期待できます。
一方、エンゲージメントは組織への愛着や貢献意欲を含むため、個人のパフォーマンス向上にとどまらず、チームや部署、ひいては組織全体に好影響が波及する点が異なります。
エンゲージメントが高い組織では、従業員間の連携が強化されたり、職場全体の雰囲気が改善されたりといった効果が見られます。
複数の調査でも、エンゲージメントの高さが企業の生産性や業績にプラスの影響を与えることが示されています。
例えば、ある調査ではエンゲージメントの高い組織は生産性が31%向上するというデータもあります。
また、収益性や顧客満足度、売上伸長率との相関関係も指摘されています。
このように、個人の生産性をダイレクトに高めたい場合はモチベーション向上施策が有効な一方、チームワークの強化や企業文化の醸成を通じて組織全体の力を底上げしたい場合には、エンゲージメント向上施策がより効果的と言えるでしょう。
以上、3つの点でエンゲージメントとモチベーションの違いを表にまとめると、下記のようになります。
| 観点 | エンゲージメント | モチベーション |
|---|---|---|
| 関係性の方向性 | 組織と従業員の「双方向」的なつながり | 個人の目標達成に向けた「一方向」的な意欲 |
| 持続性 | 長期的に持続しやすい性質 | 短期的に変動しやすい性質 |
| 影響の範囲 | 組織全体の活性化に影響 | 主に個人のパフォーマンスに影響 |
エンゲージメントとモチベーションの関係性
エンゲージメントとモチベーションは、全く無関係な独立した概念ではなく、むしろ、エンゲージメントとモチベーションは相互に影響し合い、密接に関係する概念です。
どちらか一方だけを高めるのではなく、両者の間に好循環を生み出すことが、組織全体の力を最大限に引き出す鍵となります。
まず、「エンゲージメントがモチベーションの土台となる」側面について見ていきましょう。
組織に対する愛着や信頼、貢献したいという強い思い(エンゲージメント)があるからこそ、従業員は日々の業務や個人目標の達成に対して高い意欲(モチベーション)を維持しやすくなります。
組織との間に安定した心理的なつながりが築かれている状態は、従業員が安心して仕事に取り組み、困難に直面しても前向きに乗り越えようとする意欲を下支えする基盤となるのです。
次に、「モチベーションがエンゲージメントを高める」側面も存在します。
仕事を通じて成長を実感したり、目標を達成して成功体験を積んだりすること(モチベーションが満たされること)は、従業員の自己肯定感を高め、働くことへの喜びややりがいにつながります。
こうしたポジティブな経験が積み重なることで、「この組織で働くことに価値がある」「もっと組織に貢献したい」という気持ちが強まり、結果として組織への愛着や貢献意欲、つまりエンゲージメントの向上につながっていきます。
「エンゲージメント向上によってモチベーションも高まる」といった好循環が生まれる可能性は、多くの知見で示唆されています。
一方、注意すべき点として「モチベーションは高いがエンゲージメントは低い」という状態のリスクが挙げられます。
個人のスキルアップや特定の報酬獲得といった短期的な目標達成に向けて高いモチベーションを持っていても、組織への貢献意識や共感が低い場合、そのスキルや経験を習得したらすぐに別の機会を求めて離職してしまう可能性があります。
これは、せっかく優秀な人材が育っても、組織としてその恩恵を十分に受けられない事態を招くことになります。
このように、エンゲージメントとモチベーションは一方がもう一方を促進し合う関係にありますが、そのバランスが崩れると組織にとって望ましくない結果を招くこともあります。
両者の違いを理解し、組織と個人のより良い関係性を構築することが、持続的な組織の成長には不可欠です。
高いエンゲージメントが生産性向上や離職率低下といった様々なメリットをもたらすことは、多くの調査でも明らかになっています。
エンゲージメントと類似概念の使い分け
エンゲージメントは、すでに解説したモチベーションの他に、「従業員満足度」や「ロイヤリティ(忠誠心)」といった人事用語と混同されやすい概念です。
これらは一見似ているように思えますが、それぞれが対象とする範囲や意味合いには明確な違いがあります。
「従業員満足度」との違い|満足しているが貢献意欲があるとは限らない
「従業員満足度(ES)」とは、労働条件や福利厚生、給与、人間関係など、会社から与えられる待遇や環境に対する従業員の満足度合いを示す指標です。これは、従業員が組織に対して受動的に抱く「評価」の側面が強いと言えます。
従業員満足度が高いことは良い状態ですが、それが必ずしも組織への貢献意欲に直結するわけではありません。
給与や働きやすさには満足していても、「それ以上のことはしない」といった、いわゆる「ぬるま湯社員」や「ぶら下がり社員」と呼ばれる状態は、まさにこの典型例と言えるでしょう。
満足はしていても、組織の目標達成に向けて主体的に行動する動機付けが弱い場合があります。
エンゲージメントが組織と従業員の「双方向の貢献意欲」を指すのに対し、従業員満足度は従業員から会社への「一方向の評価」に留まることが多いという点が、両者の決定的な違いです。
「ロイヤルティ(忠誠心)」との違い|対等な信頼関係か、主従関係か
従業員エンゲージメントと混同されやすい概念に「ロイヤルティ(忠誠心)」があります。
ロイヤルティは、従業員が組織に対して抱く「忠誠」や「愛着」を指す言葉です。
これは、かつての日本企業に多く見られた終身雇用や年功序列といった伝統的な雇用慣行、あるいは企業と従業員の間に主従関係があった時代の文脈で語られることが多かった概念と言えるでしょう。
エンゲージメントが組織と従業員の間の「対等な信頼関係」に基づいた「双方向」の関係性を重視するのに対し、ロイヤルティは従業員から企業への「一方向」的な感情が強いという根本的な違いがあります。
具体的に従業員の行動という点で見ると、ロイヤルティが高い従業員は、良くも悪くも企業の決定や指示に忠実に従う傾向が見られます。
一方、エンゲージメントが高い従業員は、単に従うだけでなく、組織の成長のために自発的に意見を述べたり、課題解決に向けて積極的に行動したりする姿勢が強いのが特徴です。
組織が持続的に変化に対応し、成長していくためには、指示待ちではなく、従業員一人ひとりが主体的に関わるエンゲージメントの関係性がより重要になると言えます。
企業がエンゲージメント向上に取り組むべき3つのメリット
企業がエンゲージメント向上に力を入れることで得られる主要なメリットとして、「生産性の向上」「優秀な人材の定着」「従業員の自律的な行動やイノベーションの促進」の3点について紹介します。
生産性の向上と業績への好影響
従業員エンゲージメントが高い状態にあると、一人ひとりが自身の業務に誇りを持ち、組織への貢献意欲が生まれます。
これにより、指示を待つのではなく、自ら積極的に課題を見つけ、解決策を考えながら仕事を進めるようになります。
その結果、個々の業務の質やスピードが向上し、個人の生産性が高まる効果が期待できます。
個々の従業員の生産性向上は、単にその人だけの成果に留まりません。
チーム内での円滑なコミュニケーションや協力体制の強化、活発な情報共有を促し、相乗効果を生み出します。
これにより、チームや部署全体、さらには組織全体の生産性向上へとつながるメカニズムが働きます。
このような生産性の向上は、企業の業績に直接的な好影響をもたらします。
例えば、業務効率化によるコスト削減、顧客満足度の向上、そして革新的なアイデアの創出は、売上や利益の増加に結びつくためです。
実際、ある調査ではエンゲージメントスコアが1ポイント上昇することで、営業利益率が0.35%上昇する可能性が示唆されています。また、ワークエンゲージメントが高い企業ほど、労働生産性が1〜2%ほど上昇するというデータもあります。エンゲージメント向上は、企業の持続的な成長に不可欠な要素と言えるでしょう。
優秀な人材の定着と離職率の低下
エンゲージメントが高い従業員は、自身の所属する組織に対し、強い愛着や一体感を抱きます。
これにより、「この会社で働き続けたい」「組織に貢献したい」という意識が生まれることから、たとえ他社からより良い条件を提示されても、安易に転職を考える可能性が低くなります。
これは、単に待遇への満足だけでなく、仕事そのものへのやりがいや組織への貢献実感を得られているからです。
特に、企業にとって重要な役割を担う優秀な人材ほど、待遇面に加えて、自身の成長機会やキャリアパス、組織への貢献といった非金銭的な要素を重視する傾向が強いと言えます。
エンゲージメントが高い状態は、こうした欲求を満たす上で非常に有効であり、結果として優秀層のリテンション(人材定着)に大きく寄与します。
リンクアンドモチベーション社の調査でも、エンゲージメントと退職率には強い逆相関関係があることが報告されています。
また、厚生労働省の調査では、ワークエンゲージメントが高い企業ほど離職率が低下する傾向が示されており、スコアの高い企業は低い企業に比べて離職率が約2倍低いというデータがあります。
離職率の低下は、企業経営上も直接的なメリットがあります。
新たな人材の採用にかかるコストや労力、そして新入社員の教育・研修にかかるコストを削減できます。
これにより、削減できた経営資源を、より生産的な分野や企業の成長戦略に投資することが可能になります。
実際に国内製造業の事例では、エンゲージメント向上に向けた取り組みの結果、離職者数が3年間で20%以上減少したという報告もあり、人材定着は企業力の強化に不可欠な要素と言えます。
従業員の自律的な行動やイノベーションの促進
エンゲージメントが高い従業員は、自身の業務を単なるタスクとしてではなく、組織の目標達成に貢献する「自分ごと」として深く捉えます。
このような意識は、与えられた指示を待つのではなく、自ら積極的に業務上の課題を発見し、解決策を考え、行動に移すといった「自律性」を育みます。
さらに、組織への信頼や貢献意欲が高い状態にあると、従業員は自身のアイデアや意見を率直に提案しやすくなります。
たとえ失敗を恐れずに新しい挑戦ができるような、心理的安全性が確保された組織文化が醸成されやすくなります。
これにより、従業員一人ひとりの主体性や創造性が刺激され、部署や組織全体のイノベーション創出につながります。
変化の激しい現代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、こうした従業員の自律的な行動や、ボトムアップでのイノベーションが不可欠です。
エンゲージメントの向上は、これらの要素を引き出し、組織全体の変革力と成長スピードを高める上で重要な役割を果たします。
【実践】エンゲージメントとモチベーションを高める具体的な施策例
これまで、エンゲージメントとモチベーションそれぞれの定義や違い、相互の関係性について詳しく解説してきました。
これらの理解を踏まえ、本章では両者を高めるための具体的な施策について掘り下げていきます。
エンゲージメントを高めるためのアプローチ
従業員のエンゲージメントを高めるためには、企業と従業員の間にポジティブな心理的なつながりを育むための多角的なアプローチが必要です。
まず、企業のビジョンやパーパスを従業員に深く浸透させることが重要です。
経営層からの定期的なメッセージ発信やビジョン共有ワークショップの開催などを通じて、従業員一人ひとりが自身の業務が組織の目標達成にどう貢献しているかを実感できる機会を増やします。
アコム株式会社のビジョンブック作成や、株式会社ノースサンドの全社員集会なども有効な手段と言えるでしょう。
次に、心理的安全性を確保し、上司や同僚との信頼関係を深めるためのコミュニケーション施策を実施します。
定期的な1on1ミーティングの定着化や、部署横断プロジェクトの推進、感謝の気持ちを伝え合うピアボーナス制度(Uniposなどの導入事例あり)やサンクスプレゼント活動(大東建託グループ事例)などが効果的です。
オープンな対話が可能な環境は、従業員が安心して意見を述べ、連携を深める土台となります。
さらに、従業員が「この会社で成長できる」と感じられるよう、挑戦的な業務のアサインやキャリア開発の機会を提供することも欠かせません。
ストレッチ目標の設定、社内公募制度、研修・資格取得支援制度の拡充、スキルマップの活用(KECグループ事例)などが挙げられます。
個人の成長をサポートする体制は、長期的なエンゲージメントにつながります。
エンゲージメントを高めるための主なアプローチと施策例
| アプローチ(柱) | 具体的な施策例 |
|---|---|
| ビジョン・パーパスの浸透 | 経営層からのメッセージ発信、ビジョン共有ワークショップ、ビジョンブック作成、全社員集会 |
| 心理的安全性・信頼関係の醸成 | 1on1ミーティング、部署横断プロジェクト、ピアボーナス制度、サンクスプレゼント活動 |
| 成長支援 | 挑戦的な業務のアサイン、キャリア開発の機会提供、ストレッチ目標設定、 社内公募制度、研修・資格取得支援、スキルマップ活用 |
| 評価・称賛 | 成果・プロセス評価、人事評価制度見直し、社内表彰制度、能力評価制度 |
最後に、従業員の貢献を正当に評価し、称賛する文化を醸成します。
成果だけでなく、そこに至るプロセスも評価する人事評価制度への見直しや、社内表彰制度の活性化(株式会社プログリット事例)、能力評価制度の制定(株式会社丸井グループ事例)などが有効です。
貢献が可視化され、認められることで、従業員の組織への愛着と貢献意欲はさらに高まるでしょう。
モチベーションを向上させるための取り組み
モチベーションは、個人の目標達成に向けた意欲を高めることが中心となります。
そのため、従業員の内面から湧き出る「やりがい」や「成長実感」といった内発的動機づけと、報酬や評価などの外部からの働きかけである外発的動機づけの両面からアプローチすることが重要です。
具体的には、以下の取り組みが効果的です。
- 人事評価制度の構築
従業員の成果やプロセスを正当に評価するため、公平かつ透明性の高い制度を構築することが効果的です。
評価項目や基準を明確にし、評価結果が昇進や報酬に適切に結びつく仕組みは、目標達成への強い動機づけとなります。
中古車販売を手がけるA社のように、氏名や性別を伏せた資料で評価を行う工夫も、公平性の担保につながります。
- キャリアプラン支援
従業員一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、成長を支援する仕組みも欠かせません。
定期的な1on1ミーティングでの個人の目標設定やフィードバック、スキルアップのための研修や学習機会の提供、さらには挑戦したい業務へのジョブポスティングや社内公募制度といったキャリア開発支援は、自己実現への意欲を高めるでしょう。
- 称賛文化の醸成
挑戦や成果を称賛する文化の醸成も重要です。金銭的なインセンティブだけでなく、表彰制度や社内でのポジティブな称賛は、個人の貢献意欲を刺激し、さらなる高みを目指す原動力となります。
これらの施策を組み合わせることで、従業員のモチベーションは効果的に高められるでしょう。
モチベーションとエンゲージメントの違いを理解し、自社に合った人材戦略を立てましょう
本記事では、従業員の「モチベーション」と「エンゲージメント」といった、人材戦略において重要な二つの概念について紹介しました。
両者は異なる概念でありながら、相互に影響し合う密接な関係にあります。
エンゲージメントがモチベーションの土台となり、モチベーションの成功体験がエンゲージメントを高める、といった好循環を生み出すことが望ましいです。
特に、現代のビジネス環境においては、個人の意欲に焦点を当てたモチベーション管理だけでなく、組織と従業員の強固な結びつきであるエンゲージメントを高めることが、企業の持続的な成長にとって不可欠です。
エンゲージメントが高い組織は、従業員一人ひとりが主体的に業務に取り組み、組織全体の生産性向上や業績への好影響をもたらすことが複数の調査で示されています。
例えば、エンゲージメントの高い組織は生産性が31%向上するというデータや、エンゲージメントスコアが高い企業ほど低い企業に比べて離職率が約2倍低いというデータもあります。
優秀な人材の定着を促し、変化への対応力やイノベーションを生み出す源泉ともなるため、エンゲージメント向上への取り組みは、現代の企業にとって避けて通れない課題と言えるでしょう。
本記事でご紹介したエンゲージメントとモチベーション、それぞれを高めるための具体的な施策例などを参考に、まずは自社の従業員の現状把握から始めるのが良いでしょう。
組織サーベイなどを活用して課題を可視化し、自社の文化や従業員のニーズに最も合った人材戦略を立案・実行していくことが重要です。
両者の違いを正しく理解し、自社に合った効果的な施策を継続的に実施することで、組織全体の力を最大限に引き出し、企業のさらなる発展につなげていきましょう。