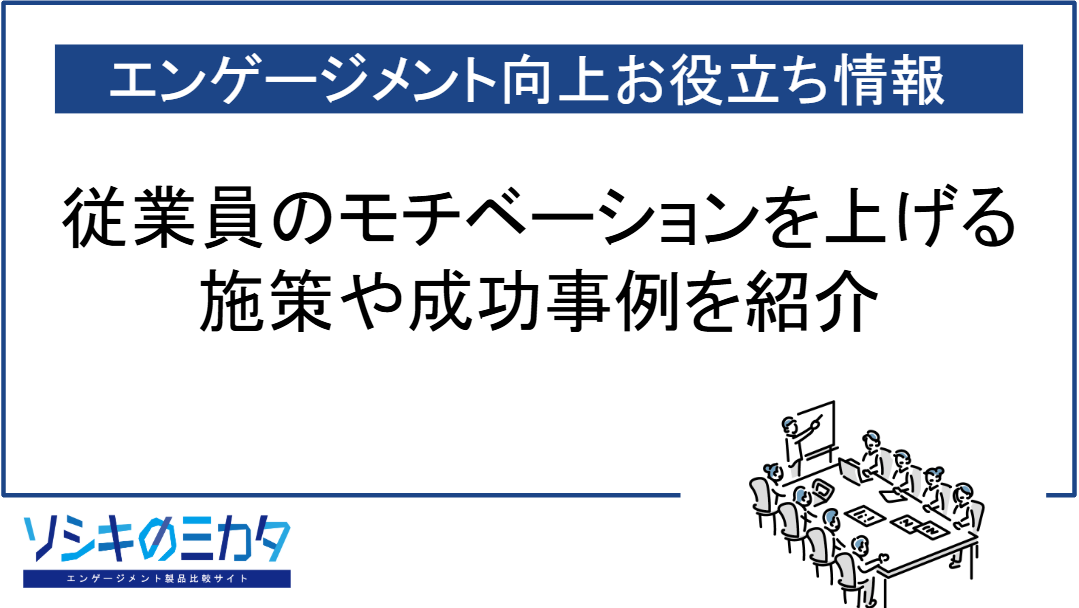【施策10選】従業員のモチベーションを上げる施策や成功事例を紹介
従業員のモチベーション向上は、企業成長に不可欠な要素です。
しかし、施策が効果を発揮するためには、組織の状況や従業員のニーズに合わせたアプローチが求められます。
この記事では、従業員のモチベーションを最大限に引き出すための、具体的な施策を10個ご紹介します。
企業が従業員のモチベーション向上に取り組むべき3つの理由
働き方が多様化し、かつてないほど人材の流動性が高まっている現代において、従業員のモチベーションをいかに維持・向上させるかは、企業が持続的に成長し続けるための極めて重要な経営課題です。
企業が今まさに従業員のモチベーション向上に取り組むべき、主要な3つの理由を詳しく解説します。
生産性の向上と業績への貢献
従業員のモチベーションが高い状態にあると、彼らは担当業務に対し主体性や探求心を持って臨むようになります。
これにより、業務遂行の質とスピードが向上し、個人の生産性が高まることが期待できます。
従業員一人ひとりのこうした前向きな姿勢と生産性の向上が、組織全体のパフォーマンスを底上げします。
実際、従業員エンゲージメントが高い企業ほど、労働生産性の向上や売上・利益の伸びが大きいという調査結果も示されており、モチベーションの高さが最終的に企業の業績に直接的に貢献する可能性が高いことがわかります。
また、高い意欲を持つ従業員は、既存業務の改善提案や新しいアイデアの創出といった、より付加価値の高い行動を自発的に起こしやすくなります。
これは企業のイノベーションを促進する原動力ともなり得ます。
さらに、意欲的な働きは提供するサービスや製品の質の向上にもつながり、結果として顧客満足度を高め、企業の競争力強化にも大きく寄与します。
離職率の低下と人材の定着
従業員のモチベーションが高い状態は、会社へのエンゲージメント、つまり貢献意欲や愛着を高めることにつながります。
エンゲージメントが高い従業員ほど、「この会社で長く働き続けたい」と自発的に考える傾向が強まることが、複数の調査で示されています。
従業員の離職には、新たな人材の採用活動にかかるコストや、一人前になるまでの育成にかかるコストなど、企業にとって決して小さくない負担が伴います。
離職率を抑制し人材が定着することは、こうした採用・育成コストの削減に直結する重要なメリットと言えます。
また、経験豊富な従業員の離職は、企業が蓄積してきた貴重なスキルや業務に関するノウハウの流出を意味します。
以下は、離職率に関するデータです。
| 項目 | 離職率 | 出典等 |
|---|---|---|
| エンゲージメントが低い従業員(1年以内) | 9.2% | 調査データ |
| エンゲージメントが高い従業員(1年以内) | 1.2% | 調査データ |
| 2022年の離職率(全体) | 15.0% | 厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果」 |
| 新規大卒就職者の3年以内離職率 | 34.9% | 厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果」 |
これらのデータが示すように、人材流出は多くの企業が直面する課題です。
モチベーション向上による人材定着は、組織全体の知識資本を守り、企業の競争力を維持・強化するためにも不可欠なのです。
企業価値と採用競争力の強化
従業員のモチベーションが高い組織は、社外からも「働きがいのある会社」として高く評価される傾向があります。
Great Place To Work® Institute Japanなどが発表する「働きがいのある会社」ランキングに代表されるように、従業員を大切にする企業文化は、企業イメージやブランド価値の向上に直結します。
従業員を大切にすることによって得られる主なメリットは以下の通りです。
- 社外からの高い評価(「働きがいのある会社」ランキングなど)
- 企業イメージおよびブランド価値の向上
- 優秀な人材獲得における優位性の確保
- ESG評価(特に「社会」の側面)の向上
- 企業の持続的な成長と競争力強化への貢献
- 長期的な企業価値の向上
こうしたポジティブな評判は、優秀な人材を獲得する上で強力な武器となります。
特に、近年ではOpenWorkや転職会議といった社員による口コミサイトが広く利用されており、給与水準や福利厚生だけでなく、企業の文化や人間関係といったリアルな働く環境の情報が、求職者の応募意思決定に大きな影響を与えています。
口コミでの評価が高い企業ほど、採用活動において有利に進められるでしょう。
さらに、投資家や顧客がESG(環境・社会・ガバナンス)要素を重視する現代において、「社会(Social)」の一要素である従業員に対する配慮は、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素と言えます。
企業が従業員を大切にする姿勢を示すことは、単なるイメージアップにとどまらず、長期的な企業価値向上に繋がります。
社員のやる気やモチベーションが下がる主な原因
多くの企業で課題となりやすい「評価・待遇」「人間関係」「仕事内容」「キャリア」という4つの観点から、モチベーションが下がる具体的な原因を紹介します。
評価や待遇に対する不公平感
従業員の仕事に対する意欲が低下する主な原因の一つに、評価や待遇に対する不公平感が挙げられます。
特に、評価基準が曖昧で、上司の主観や個人的な感情によって評価が決まっていると感じる場合、従業員は「どれだけ努力しても正当に評価してもらえない」という不満を抱きやすくなります。
こうした状況が続くと、自身の働きが適切に認められていないと感じ、努力する意欲を失うことにつながります。
また、自身が上げた成果や会社への貢献度が、給与や賞与、昇進といった待遇に適切に反映されていないと感じるケースも、モチベーション低下に直結します。
調査では、「評価の基準があいまい」であることに不公平感を覚える人が48%、「評価が報酬に反映されない」と感じる人が30%にのぼるとの結果が出ています。
「頑張っても報われない」という感覚は、従業員の諦めやエンゲージメント低下を招きます。
さらに、評価のプロセスや、どのような基準で給与や賞与が決定されるのかが従業員に開示されておらず不透明であることも、不公平感を生む大きな要因です。
なぜその評価や待遇になったのか理由が分からないことは、会社に対する不信感や疑念につながりやすく、働く上での心理的な負担となります。
職場の人間関係の悩み
従業員のモチベーションを低下させる要因として、職場の人間関係に悩みを抱えるケースは多く見られます。
厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活に関することで「強い不安、悩み、ストレス」を感じている労働者は82.7%に上り、その原因の一つに人間関係があります。
特に、上司との関係性は部下の心理的安全性に大きく影響します。
高圧的な態度やコミュニケーション不足、あるいは過度な干渉は、部下が安心して報告・連絡・相談がしにくい環境を作り出し、結果として働く意欲の低下を招きます。
また、同僚間での協力体制の欠如や対立、孤立なども、チーム全体の生産性を低下させると同時に、当事者のモチベーションを低下させる原因となります。
部署間の連携不足や風通しの悪いコミュニケーション環境も同様です。
こうした状況は従業員に孤独感や疎外感を与え、組織への貢献意欲を失わせる要因となります。
円滑な人間関係は、従業員が気持ちよく働くための基盤と言えるでしょう。
仕事内容や役割とのミスマッチ
従業員が持つスキルや興味、あるいは思い描くキャリアプランと、実際に担当する仕事内容や与えられた役割に大きなズレがある場合も、モチベーションは低下しやすくなります。
例えば、仕事内容や役割との大きなズレとして、以下のような状況が挙げられます。
- 新しく配属された部署でやりたかった仕事ができない
- クリエイティブな仕事を目指していたのに、単純な定型業務ばかり任される
このような状況は、従業員に自身の能力や個性が活かされていないという感覚を与えます。
このような状態が続くと、成長を実感できず、仕事へのやりがいを失うことにつながります。
自身の価値を発揮できないと感じることは、自己肯定感の低下を招き、仕事への意欲をさらに削いでしまいます。
また、担当業務の難易度が本人の能力に対して高すぎる、あるいは低すぎる場合も同様です。
難しすぎる仕事には達成感を得にくく、簡単すぎる仕事には退屈を感じてしまいます。
仕事内容や役割とのミスマッチは、従業員のエンゲージメントを著しく低下させ、パフォーマンスの低下や最終的な離職意向へと直結する重要な要因となります。
企業は従業員の適性や志向を把握し、適切な人員配置や業務アサインを行うことが求められます。
キャリアプランに対する将来の不安
この会社で働き続けても、自身のキャリアがどのように発展していくか、明確な道筋が見えないことも、従業員のモチベーションを低下させる大きな原因の一つとなります。
具体的にどのような役職を目指せるか、どのようなスキルを習得できるかといったキャリアパスが不明確であると、従業員は将来に漠然とした不安を抱きやすくなります。
また、日々の業務が単調なルーティンワークに偏り、自身の成長を実感する機会や、新しい分野へ挑戦できる環境が不足している状況も、やりがいを失わせる要因となります。
社内に目標とすべきロールモデルとなる先輩社員がいなかったり、キャリアについて気軽に相談できる上司やメンターのような存在が不在だったりすることも、自身の将来像を描くことを難しくします。
これらの要素が複合的に影響し、「このまま働き続けても大丈夫だろうか」という不安感が増大し、結果として働く意欲の低下につながるのです。
知っておきたいモチベーション向上の基本理論
やみくもに様々な施策を試すよりも、理論に基づいたアプローチをとることで、より効果的かつ継続的な結果に繋がりやすくなるためです。
特に、「内発的動機付け」「外発的動機付け」「ハーズバーグの二要因理論」は、従業員の「やる気」がどこから来るのかを理解し、どのような働きかけが有効かを考える上で大変役立ちます。
内側から意欲を引き出す「内発的動機付け」
従業員の「やる気」には、大きく分けて二つの種類があります。
一つは、個人の内側から自然に湧き出てくる興味や関心、好奇心に基づく意欲で、これを「内発的動機付け」と呼びます。
仕事そのものへの面白さや、新しいスキルを習得したいという探究心、目標達成への純粋な喜び、自己成長への欲求などがこれにあたります。
報酬や評価といった外部からの働きかけによる「外発的動機付け」とは異なり、内発的動機付けは行動の源泉が個人の内側にあるため、持続性が高いという特長があります。
内発的動機付けが高い従業員は、主体的に業務に取り組み、困難な課題にも粘り強く挑戦する傾向が見られます。
これにより、生産性の向上や期待を超える成果、創造性の発揮に繋がりやすくなります。
自己成長を促し、長期的な視点で高いパフォーマンスを維持するためには、この内発的動機付けを高めるアプローチが有効です。
内発的動機付けは、「自律性(自分で選択したい)」「有能感(能力を発揮したい)」「関係性(他者と繋がり貢献したい)」といった基本的な心理的欲求が満たされる環境で高まるとされています。
外からの働きかけで意欲を促す「外発的動機付け」
もう一つのモチベーションの源泉として、「外発的動機付け」があります。
これは、報酬や評価、承認、あるいは罰則といった外部からの働きかけによって生まれる意欲を指します。
例えば、昇給やインセンティブ、昇進などを目指すといった「アメ」の側面もあれば、低評価や減給、降格、懲罰などを回避したいという「ムチ」の側面もあります。
外発的動機付けのメリットは、目標が明確で行動を促しやすく、即効性が期待できる点です。
短期的な成果を上げる上では有効なアプローチと言えるでしょう。
一方で、効果が持続しにくい点がデメリットです。
また、報酬や評価の獲得自体が目的化してしまい、かえって仕事そのものへの興味や関心(内発的動機付け)を損なう「アンダーマイニング効果」が発生するリスクもあります。
特に、低評価や罰則といったネガティブな側面は、従業員の不信感につながる可能性もあるため、慎重な運用が求められます。
不満と満足の要因を理解する「ハーズバーグの二要因理論」
フレデリック・ハーズバーグが提唱した「二要因理論」とは、仕事における満足と不満足は、それぞれ異なる種類の要因によって引き起こされる、という考え方です。
従業員のモチベーションを考える上で、この理論は重要な示唆を与えてくれます。
まず、「不満」に関わる要因として「衛生要因」があります。
これには、給与や福利厚生、会社の規定や制度、労働環境、人間関係などが含まれます。
衛生要因が不十分である場合、従業員は不満を感じますが、これらが満たされても不満が解消されるだけで、仕事に対する積極的な意欲(モチベーション)が直接的に向上するわけではありません。
一方、「満足」に関わる要因は「動機付け要因」と呼ばれます。
達成感、承認、仕事そのものへの興味・関心、責任、昇進、個人の成長などがこれにあたります。
例えば、上司から「ありがとう」と感謝の言葉をかけられたり、自身の仕事が評価されたりといった「承認」は、この動機付け要因を満たします。
動機付け要因が満たされることで、従業員は仕事にやりがいを感じ、積極的にモチベーションが高まるのです。
したがって、従業員のモチベーションを効果的に向上させるためには、衛生要因を整えて不満を取り除くことはもちろん、同時に動機付け要因を充足させて満足度を高めるという、両面からのアプローチが不可欠となります。
従業員のモチベーションを向上させる具体的施策10選
企業が明日からでも実践できる具体的な施策を10個厳選してご紹介します。
全ての施策が、そのままどの企業にも当てはまるわけではありませんので、自社の課題や組織文化、従業員の特性を考慮し、最適な施策を単独で、あるいは複数組み合わせて導入してください。
会社のビジョンと個人の目標を接続する
従業員が日々の業務にやりがいや「意味」を見出し、内側から意欲を高めるためには、会社のビジョンや組織全体の目標と自身の仕事がどのように繋がっているのかを明確に理解していることが非常に重要です。
自身の業務が組織全体の成果に貢献していると実感できるとき、従業員の内発的動機付けは大きく向上します。
この接続を効果的に行うためのフレームワークとして、OKR(Objectives and Key Results)やMBO(目標管理制度)の活用が挙げられます。
これらの手法は、まず会社全体の大きな目標を設定し、それを部署やチーム、そして最終的に個人の具体的な目標へとブレイクダウンしていくものです。
例えば、OKRでは「企業、部署、個人の目標設定を連動させる」ことが特徴です。
MBOでも「目標設定時に達成すべき指標や状態、期限が明確に定められる」ことで、個人の取り組みが組織目標にどう紐づくかが見えやすくなります。
また、設定した目標に対する進捗確認や、個人の業務が組織目標へどう貢献しているかを具体的に伝える場として、定期的な1on1ミーティングが有効です。
上司が部下に対し、「あなたのこの業務が、会社のこの目標達成に不可欠である」と丁寧に説明することで、従業員は自身の役割の重要性を認識し、より高い納得感を持って業務に取り組めるようになります。
納得感のある公正な評価制度を構築する
従業員のモチベーション低下の大きな要因の一つは、評価に対する不公平感です。
自身の貢献が正当に評価されていないと感じると、働く意欲は大きく削がれてしまいます。
逆に、評価が公正に行われ、自身の努力や成果がしっかりと認められるという期待感は、従業員の会社へのエンゲージメントを大きく高める要因となります。
納得感のある評価制度を構築するためには、以下の要素が重要です。
- 評価基準を具体的かつ明確に設定し、全従業員に公開すること。MBO(目標管理制度)やOKR(目標と主要な結果)などのフレームワークを活用し、定量的目標と定性目標のバランスを取りながら、達成すべき指標や状態を明確に定めます。目標設定のプロセスに従業員自身が関わる機会を設けることも、納得感を醸成する上で重要です。
- 評価者の主観によるブレを防ぎ、多角的な視点を取り入れるために、360度評価(多面評価)の導入も有効です。評価者に対する適切なトレーニングを実施することも、評価の質の向上につながります。
- 評価結果を単に伝えるだけでなく、丁寧なフィードバック面談の場を設けること。評価の根拠や今後の期待を具体的に伝えることで、従業員は自身の強みや改善点を理解し、成長意欲を高めることができます。
これが、次期の具体的な行動へとつながり、さらなる成果を引き出す原動力となるでしょう。
金銭・非金銭的なインセンティブを設計する
従業員のモチベーションを高める上で、インセンティブ制度の導入は有効な施策の一つです。
インセンティブには、主に金銭的な報酬と非金銭的な報酬の二種類があります。
金銭的インセンティブは、賞与や業績連動報酬、ストックオプションなどが代表的です。
例えば、Amazonでは配送件数に応じて報酬が付与されるなど、短期的な成果や目標達成への意欲を直接的に高める効果が期待できます。
これらの金銭的な報酬は、従業員の経済的な満足度向上につながり、特定の行動を強く促す力があります。
一方、非金銭的インセンティブは、承認欲求を満たし、より長期的なエンゲージメントを育む上で重要です。
表彰制度、希望する研修への参加機会、特別休暇などがこれにあたります。
また、物質的な報酬として旅行券やテーマパーク利用券、社内通貨やポイント制度(株式会社ベネフィット・ワンの事例など)も活用されています。
評価に反映する形でリーダーへの登用、希望するチームへの配置、難易度の高い業務のアサインなども非金銭的インセンティブに含まれます。
これらは、従業員の成長実感や帰属意識を高め、「この会社に貢献したい」という内発的な動機付けにもつながります。
効果的なインセンティブ制度を設計するには、評価基準の透明性と公平性を確保することが不可欠です。
また、金銭的報酬と非金銭的報酬をバランス良く組み合わせることで、従業員の多様なニーズに応え、持続的なモチベーション向上を図ることができるでしょう。
成長を実感できるキャリアプランを提示する
従業員が「この会社でどのように成長できるのか」「どのようなキャリアパスがあるのか」といった自身の将来像を明確に描けない場合、漠然とした不安を感じ、仕事への意欲が低下することがあります。
キャリアプランを提示し、自身の努力が将来につながるイメージを持たせることは、目標達成に向けた学習意欲を喚起し、仕事へのやりがいや成長実感につながります。
企業は、職種や役職ごとに複数のキャリアパスをモデルとして示し、従業員が自身の将来を具体的にイメージできるよう支援することが効果的です。
例えば、専門性を追求する「スペシャリストコース」や、組織を率いる「マネジメントコース」といった選択肢を明確に提示することで、目指すべき方向性が見えやすくなります。
また、定期的な1on1面談などを通じて、上司が部下のキャリアに関する希望や悩みについて丁寧にヒアリングし、個々の目標設定や成長プランの策定をサポートする体制を整えることも重要です。
これにより、従業員は自身のキャリアについて、会社から支援されているという安心感を得られます。
設定したキャリアプランを単なる絵空事にしないためには、以下の要素を連携させることが重要です。
- 社内公募制度
- 目標達成・スキル習得に必要な研修制度
- 業務アサインメント
具体的な行動を通じて成長を実感できる仕組みを構築することで、従業員のモチベーションを高く維持し、主体的なキャリア形成を促進できます。
挑戦を促すための裁量権を委譲する
従業員のモチベーションを内側から高める有効な施策の一つに、業務に関する一定の判断や意思決定を任せる「裁量権の委譲」があります。
これは「エンパワーメント」とも呼ばれ、部下に権限の一部を与えることで、仕事への「やらされ感」を払拭し、当事者意識や責任感を醸成する効果が期待できます。
自身の裁量で物事を進める経験は、従業員に自己肯定感や有能感をもたらし、さらなる成長への意欲を引き出します。
結果として、仕事そのものに対する内発的な動機付けが促進されるのです。
ただし、裁量権の委譲は単なる「丸投げ」とは明確に異なります。
上司は最終的な責任を持ちつつ、権限を与えた部下の業務について定期的に進捗を確認し、必要なサポートを提供することが不可欠です。
また、挑戦に伴う失敗を頭ごなしに否定せず、次に活かすための建設的なフィードバックを行い、失敗を許容する文化を醸成することも重要となります。
「どこから権限を委譲すれば良いか分からない」という企業は、比較的小さな範囲から始めることができます。
例えば、以下のようなスモールスタートが考えられます。
- 業務スケジュールの自己管理を任せる
- 小規模な予算の決定権を与える
- 担当プロジェクト内での手法選択を自由にさせる
スキルや特性を活かした人員配置を行う
従業員が自身の強みや得意分野を仕事で最大限に発揮できる環境は、その人自身の内側から湧き上がる意欲、すなわち内発的動機付けを大きく刺激します。
自身のスキルが組織への貢献に繋がっているという実感は、仕事に対するやりがいや貢献感を高め、結果としてモチベーション向上に直結します。
企業にとっても、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出す「適材適所」の人員配置は、組織全体の生産性向上に不可欠です。
最適な人員配置を実現するためには、まず従業員一人ひとりのスキル、経験、潜在能力、さらにはキャリアに対する志向などを正確に把握することが重要です。
現状把握の主な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- タレントマネジメントシステムを活用し、スキルや経験、潜在能力、キャリア志向などの情報をデータとして一元管理・可視化する
- 定期的な1on1面談で、丁寧なヒアリングを行う
- 従業員からの自己申告制度を設ける
把握した客観的なデータや本人の希望を踏まえ、個人の強みが最大限活かされる部署やプロジェクトへの配置を検討します。
その際は、会社の事業戦略とのすり合わせを丁寧に行い、なぜその配置が最適なのかを本人にしっかりと説明し、納得感を醸成することが欠かせません。
しかし、配置転換はあくまでスタート地点です。
異動後に本人が新しい環境で活躍できているか、新たな課題に直面していないかを定期的に確認し、必要なサポートを継続的に行う体制が、従業員のモチベーション維持・向上には不可欠となります。
「ありがとう」が飛び交うサンクスカード制度を導入する
従業員同士が日々の感謝や称賛の気持ちをメッセージとして伝え合う「サンクスカード制度」の導入も有効な施策の一つです。
これは、普段改めて口にする機会の少ない「ありがとう」や小さな貢献への感謝を可視化し、互いの良い点や頑張りを認め合う文化を組織に根付かせることを目的としています。
従業員一人ひとりの仕事が誰かの役に立っていることを実感する機会を生み出すでしょう。
サンクスカード制度がモチベーション向上に寄与するのは、受け取った側が自身の仕事について他者から感謝され、認められていると感じられるためです。
これにより承認欲求が満たされ、自己肯定感が高まります。
また、感謝のやり取りは社内のポジティブな人間関係を築き、働く上での安心感にもつながるでしょう。
制度を成功させるには、運用上の工夫が鍵となります。
物理的なカードだけでなく、手軽に利用できる専用アプリでの運用も検討しましょう。
さらに、サンクスカードの送受信に対して社内ポイントを付与してインセンティブと交換できるようにしたり、積極的に活用している従業員や優れた内容を表彰したりするなど、参加を促す仕組みを取り入れると、制度の活性化につながりやすくなります。
社内コミュニケーションを活性化させる仕組みを作る
従業員のモチベーション維持には、孤立感の解消や心理的安全性の確保が不可欠です。
良好な人間関係は職場の雰囲気を和やかにし、安心して意見交換や相談ができる環境は、従業員の働く意欲向上につながります。
コミュニケーションを活性化させる具体的な施策として、業務時間外の交流機会を設けることが有効です。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 他部署のメンバーと交流するシャッフルランチ
- 部活動
- 社員同士や家族も参加できる社内イベント
また、日常的なやり取りを促すために、Slackなどのチャットツールに気軽に雑談できるチャンネルを設けたり、フリーアドレス制を導入して部署を超えた偶発的なコミュニケーションを促進したりする方法もあります。
これらの施策は、従業員が自発的に参加したくなるような工夫(参加の任意性や魅力的な企画)を凝らし、目的を明確にして運用することが成功の鍵となります。
ワークライフバランスを整えリフレッシュを促進する
従業員が心身ともに健康な状態で働くためには、仕事と私生活のバランス、すなわちワークライフバランスの充実は欠かせません。
十分な休息やリフレッシュの時間は、仕事への集中力や創造性を高める源となります。
一方で、長時間労働は疲弊を招き、従業員の意欲を著しく低下させるだけでなく、健康被害のリスクも高めます。
厚生労働省は中小企業における長時間労働の是正を推進しており、多くの企業がこの課題に取り組んでいます。
ワークライフバランスを整えるための具体的な施策としては、以下が挙げられます。
- 長時間労働の是正: 定時退社を促すノー残業デー(運送業B社の事例など)や、労務管理システムの導入による労働時間の適切な把握。
- 柔軟な働き方の導入: テレワークやフレックスタイム制度(三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社の事例など)など、時間や場所にとらわれない働き方の選択肢を提供。
- 休暇取得の促進: 有給休暇の計画的付与や、リフレッシュ休暇制度の導入など、従業員が休みを取りやすい環境整備。
これらの制度を整えることで、従業員は自身のライフスタイルに合わせた働き方が可能になり、会社への満足度が高まります。
結果として、エンゲージメントや生産性の向上、離職率の低下といった効果が期待できます。
ワークライフバランスの推進は、3000社以上の企業で導入されており、企業規模を問わず有効な施策です。
スキルアップを支援する研修や教育制度を充実させる
従業員が「自分は成長できている」と実感できることは、仕事への自信や会社への貢献意欲を高め、モチベーション向上に直結する重要な要素です。
企業が従業員のスキルアップを組織として支援する体制を整えることは、個人の成長意欲を刺激し、結果として組織全体の能力向上にもつながります。
具体的な研修・教育制度としては、まず役職や経験年数に応じた「階層別研修」が挙げられます。
新入社員にはビジネスマナーや基礎スキル、管理職にはマネジメントスキルやリーダーシップなど、各階層で求められる能力を習得する機会を提供します。
特定の専門知識・技術を深める「専門スキル研修」や、自己啓発を後押しする「資格取得支援制度」も有効です。
さらに、時間や場所を選ばずに学習できる「eラーニング」(伊藤忠商事の事例など)は、柔軟な学びを支援します。
こうした制度をより効果的にするためには、従業員がどのようなスキルを身につけたいかをヒアリングし、ニーズに合わせた内容とすることが大切です。
また、研修で習得した知識やスキルを実際の業務で実践する機会を提供することで、学びを定着させ、モチベーション維持につなげることができるでしょう。
【企業規模・業種別】モチベーション向上施策の成功事例3選
これまで、従業員のモチベーションに関する理論や、企業が実践できる具体的な施策について解説してきました。
本章では、それらの施策が実際の企業でどのように導入され、どのような成果を上げているのかを、具体的な成功事例を通して紹介します。
株式会社プレナス:タレントパレット活用によるコンディション把握と離職率低下
株式会社プレナスは、「ほっともっと」や「やよい軒」などを全国に展開する飲食チェーン企業です。
2,800店舗以上という規模で多様な働き方をする従業員がいる中で、一人ひとりの正確なコンディションを把握し、それに伴う離職を防ぐことは大きな課題となりがちです。
このような課題解決の一助として、人材活用プラットフォームであるタレントパレットのようなツールの導入が考えられます。
タレントパレットは従業員情報を一元管理し、アンケート機能などで定期的にコンディションを可視化・分析することを可能にします。
収集されたデータからコンディション低下の兆候を早期に察知し、上長による面談や適切なケアを行う運用フローを構築することで、個々の従業員に寄り添ったきめ細やかなフォローが実現します。
その結果、従業員の安心感やエンゲージメント向上、そして離職率の抑制といった効果が期待できます。
株式会社メルカリ:ピアボーナス制度「mertip」による承認文化の醸成
株式会社メルカリでは、組織の急拡大に伴い、従業員間のコミュニケーションが希薄化し、日々の「小さな貢献」が見えにくくなるという課題を抱えていました。
この課題に対し、同社が導入したのがピアボーナス制度「mertip(メルチップ)」です。
Uniposを活用したこの制度は、従業員同士が感謝や称賛の気持ちを、少額のインセンティブ(週に400ポイントなど)と共に送り合える仕組みです。
「mertip」の導入によって、部署や役職を超えた従業員間の称賛が飛躍的に増加しました。
多い時には1日に1,000件近い投稿があるなど、互いを積極的に認め合う「承認文化」が社内に醸成されています。
これにより、従来の評価制度では捉えきれなかった日々の見えにくい貢献が可視化され、従業員のモチベーション向上に繋がっています。
成功の要因としては、以下の点が挙げられます。
- Slackなど日常的に利用するツール上で手軽に利用できる利便性の高さ
- 同社の「Go Bold(大胆にやろう)」といったバリュー(価値観)と制度が強く結びついている点
この施策は、コミュニケーション活性化や人材定着にも寄与しています。
株式会社BP:「TUNAG」活用によるコミュニケーション活性化と定着率改善
ブライダル事業を中心に多角的な事業を展開する株式会社BPは、パティスリーや飲食店など多店舗を運営する中で、店舗間のコミュニケーション希薄化や情報共有の課題に直面していました。これにより、現場で働く従業員、特にアルバイトスタッフの間に孤立感が生まれやすく、定着率の低下が課題となっていました。
この状況を改善するため、同社は社内SNS機能を持つエンゲージメントツール「TUNAG」を導入しました。TUNAGを通じて、各店舗の優れたサービス事例や成功事例を全社にリアルタイムで共有する仕組みを構築しました。また、社長からの定期的なメッセージ発信なども行い、経営層と現場の距離を縮め、会社のビジョンや理念の浸透を図りました。
こうした積極的なコミュニケーション活性化の取り組みは、従業員同士の横の連携を強化し、会社への一体感やエンゲージメントを高めることにつながりました。その結果、特に課題であったアルバイトスタッフの離職率が大幅に改善するなど、組織全体の定着率向上に貢献しています。多拠点を持つ企業にとって、情報共有を円滑にするツール活用は、エンゲージメントや定着率向上に有効な手段と言えます。
施策の効果を最大化するモチベーション管理・向上ツール、サービス
モチベーションを管理する、もしくは向上させるツールやサービスの概要とそのメリットについてそれぞれ紹介します。
従業員のコンディションを可視化するサーベイツール
従業員のコンディションを可視化するサーベイツールは、従業員の心身の健康状態やエンゲージメントレベルを、簡単なアンケートを通じて定期的に測定・可視化するツールです。
特に、短期間で繰り返し実施する「パルスサーベイ」が主流となっています。
月に1回などの頻度で実施されることが多く、匿名性を保つことで従業員の本音を引き出しやすい特長があります。
このツールを活用することで、個々の従業員や部署ごとのコンディション変化をデータとして客観的に把握できます。
これにより、モチベーション低下や離職リスクの兆候を早期に発見し、問題が深刻化する前に適切な対策を講じることが可能です。
収集したデータは、様々な形で活用できます。
マネージャーはデータに基づき、課題のある従業員と1on1面談を実施し、具体的なフォローを行えます。
また、人事は組織全体の傾向を分析し、部署ごとの課題を特定して改善策を立案するなど、データに基づいた人事施策の実行に役立てられます。
このように、サーベイツールは従業員の声を組織改善につなげる上で有効な手段となります。
感謝を送り合うピアボーナス・サンクスカードツール
従業員同士が日々の業務における感謝や称賛の気持ちを、ポイントやメッセージといった形でリアルタイムに送り合えるデジタルツールは、「ピアボーナス・サンクスカードツール」と呼ばれます。
これは、特に上司の目が届きにくい、いわゆる「縁の下の力持ち」的な貢献を可視化する効果が期待できます。
同僚からの温かいメッセージや評価(社会的承認)は、従業員の自己肯定感を高め、会社へのエンゲージメント向上に繋がり、結果として働くモチベーションを大きく引き出すことになります。
特にリモートワーク環境下では、偶発的なコミュニケーションや感謝を伝える機会が減少しがちです。
このようなツールを活用することで、従業員間のポジティブなやり取りを促進し、組織の一体感を醸成する効果も期待できます。
具体的な機能としては、受け取ったポイントを商品やインセンティブと交換できるピアボーナス機能や、称賛内容を全社で共有するタイムライン機能などがあります。
企業の行動指針や大切にしたいバリューをハッシュタグとして活用することで、称賛の文化を定着させ、心理的安全性の高い前向きな人間関係の構築に貢献できるでしょう。
定期的な1on1をサポートする面談管理ツール
上司と部下による定期的な1対1の対話(1on1)は、従業員のモチベーション維持において非常に重要です。
個人のキャリアに対する漠然とした不安の解消や、目標設定のすり合わせを行う場として機能し、従業員が自身の成長を実感し、前向きに業務に取り組むための土台となります。
しかし、1on1を継続的に実施し、その質を担保することは容易ではありません。
面談管理ツールは、こうした課題を解決し、1on1が単なる雑談や報告会で終わることを防ぎ、より効果的な対話を実現するために活用できます。
ツールには、主に以下のような機能が搭載されています。
- アジェンダの事前共有と設定
- 面談内容や進捗、決定事項の履歴蓄積と可視化
- 次回までのネクストアクションの管理とリマインダー
これらの機能を活用することで、対話内容に基づいた継続的なフォローアップがスムーズに行えるようになります。
個々の従業員の状態やニーズを正確に把握し、タイムリーかつ適切なサポートを提供することで、従業員の成長を効果的に支援し、エンゲージメント向上に繋がることが期待できます。
自社に合った施策から始め、従業員がいきいきと働ける組織を作りましょう
この記事では、従業員のモチベーション向上が企業成長にいかに不可欠であるか、その重要性、やる気が低下する原因、そして具体的な施策について解説しました。
生産性向上や離職率低下、企業価値向上といったモチベーション向上がもたらす効果は、持続的な組織運営において見過ごすことはできません。
評価制度や人間関係、キャリア形成に関する不安など、モチベーション低下の原因が多岐にわたることもご理解いただけたかと思います。
また、内発的・外発的動機付けや二要因理論といった基本理論を理解することで、より効果的な施策の方向性が見えてくることにも触れました。
今回ご紹介した10個の具体的施策や成功事例は、あくまで一例です。
企業の状況や組織文化、従業員の構成はそれぞれ異なります。
そのため、全ての施策を一度に導入する必要はありません。
大切なのは、まず自社の現状をしっかりと把握し、従業員のモチベーション低下の根本原因を見極めることです。
その上で、特定された課題に対して最も有効と思われる施策や、比較的着手しやすい施策から、スモールスタートを切ることをお勧めします。
従業員一人ひとりが仕事にやりがいを感じ、能力を存分に発揮しながらいきいきと働ける組織は、結果として高いパフォーマンスを発揮し、変化の激しい時代においても持続的に成長していく、強固な基盤となります。
本記事が、貴社が従業員のエンゲージメントを高め、より良い組織を築いていくための一助となれば幸いです。